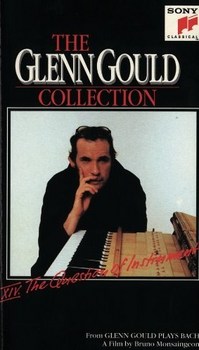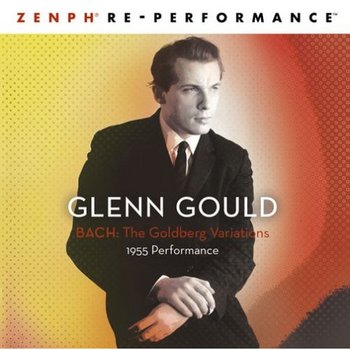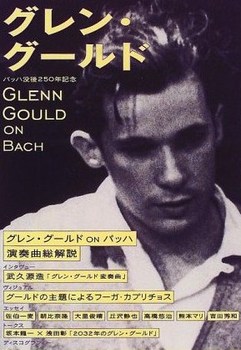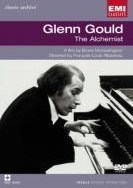Bach on Piano [Gould]
今年はGouldの没後30年です。
そのためではないのでしょうが、去年あたりから次々と新しい本やCD、DVD、映画などがでてきました。
いつでも、この人の市場は賑やかですね。
でも、私が待っているものは結局出てこなかったなぁ・・・
いつか出てくるのかなぁ・・・
私がずっと以前から、首をとてもロングにして待ち続けているもの、それは↓です。
Gouldコレクション vol.2 に収められている映像。
ブルーノ・モンサンジョンとの対話で、Bachをとことん語りつくしているのだそうです。
コレクションvol.1 は3年前(もうそんなになるんだ・・・)のクリスマスに全巻DVD化されて発売になりました。
vol.2 の第13巻は「ゴールドベルク変奏曲」として単独で発売されています。
おととしのクリスマスも去年のクリスマスも期待して待っていましたが、その続編は結局出なかったんだ・・・(ブツブツ)
この14巻は、VHSやレーザーディスクなら入手可能なのですが、プレミアがついて36.800円になってる。
たっけ~~~!!無理、無理![[雨]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/3.gif)
これ見たい!
どうしても見たい!!
見たいんだ~~!!!![rawrrs5ds[1].gif](https://glennmie.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_878/glennmie/m_rawrrs5ds5B15D.gif)
と暴れていたら、このお正月に、youtubeに上がっていました。
どちらさんか存じませんがウルトラ良い人だ。特大感謝です。
早速、こちら↓
凄い、凄い。
面白い。
さすがGouldだ、素晴らしい。![racoon[1].gif](https://glennmie.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_878/glennmie/m_racoon5B15D.gif)
Bachをピアノで再現する意味。
深く同感です。
Bachの音楽は「音楽」そのもの、楽器が変わってもどんな表現スタイルに置き換えられても、
その価値が変わってしまうことは決してないのだと。
(ついでに言うと、私のようなものがどんなヘタクソ演奏をしても、それでも全然OKな度量の深い世界なんだと確信できました。)
ピアノは使い方次第、ってこの前の記事のトリスターノの発言とも共通する。
小プレリュードの4番を次々とスタイルを変えて演奏するシーンには、感激。
モンサンジョンのエアー・ヴァイオリンのシーンには爆笑。
ショパンとプレイエルのくだりは・・・いやいや、これは少々詭弁だね(笑)
動画の続きでは、平均律のフーガの分析(これ、凄い)や、クロマティック・ファンタジーとイタリアン・コンチェルトをボロクソにけなすシーン、6曲のパルティータに対する言及とか、とにかく、とてもとても面白いです。
是非、続きもご覧になってくださいね。
そして、圧巻なのがこのシーン。BWV878 のアナリーゼです。
もう~~~~、素晴らしい!
そのためではないのでしょうが、去年あたりから次々と新しい本やCD、DVD、映画などがでてきました。
いつでも、この人の市場は賑やかですね。
でも、私が待っているものは結局出てこなかったなぁ・・・
いつか出てくるのかなぁ・・・
私がずっと以前から、首をとてもロングにして待ち続けているもの、それは↓です。
Gouldコレクション vol.2 に収められている映像。
ブルーノ・モンサンジョンとの対話で、Bachをとことん語りつくしているのだそうです。
コレクションvol.1 は3年前(もうそんなになるんだ・・・)のクリスマスに全巻DVD化されて発売になりました。
vol.2 の第13巻は「ゴールドベルク変奏曲」として単独で発売されています。
おととしのクリスマスも去年のクリスマスも期待して待っていましたが、その続編は結局出なかったんだ・・・(ブツブツ)
この14巻は、VHSやレーザーディスクなら入手可能なのですが、プレミアがついて36.800円になってる。
たっけ~~~!!無理、無理
これ見たい!
どうしても見たい!!
見たいんだ~~!!!
![rawrrs5ds[1].gif](https://glennmie.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_878/glennmie/m_rawrrs5ds5B15D.gif)
と暴れていたら、このお正月に、youtubeに上がっていました。
どちらさんか存じませんがウルトラ良い人だ。特大感謝です。
早速、こちら↓
凄い、凄い。
面白い。
さすがGouldだ、素晴らしい。
![racoon[1].gif](https://glennmie.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_878/glennmie/m_racoon5B15D.gif)
Bachをピアノで再現する意味。
深く同感です。
Bachの音楽は「音楽」そのもの、楽器が変わってもどんな表現スタイルに置き換えられても、
その価値が変わってしまうことは決してないのだと。
(ついでに言うと、私のようなものがどんなヘタクソ演奏をしても、それでも全然OKな度量の深い世界なんだと確信できました。)
ピアノは使い方次第、ってこの前の記事のトリスターノの発言とも共通する。
小プレリュードの4番を次々とスタイルを変えて演奏するシーンには、感激。
モンサンジョンのエアー・ヴァイオリンのシーンには爆笑。
ショパンとプレイエルのくだりは・・・いやいや、これは少々詭弁だね(笑)
動画の続きでは、平均律のフーガの分析(これ、凄い)や、クロマティック・ファンタジーとイタリアン・コンチェルトをボロクソにけなすシーン、6曲のパルティータに対する言及とか、とにかく、とてもとても面白いです。
是非、続きもご覧になってくださいね。
そして、圧巻なのがこのシーン。BWV878 のアナリーゼです。
もう~~~~、素晴らしい!
Gouldのソヴィエト音楽論 [Gould]
今、ショスタコーヴィッチのことをいろいろ学ぼうとしているのですが、知れば知るほどよくわかんない。
音楽作品は純粋に「音楽」として捉えたい。
作曲家の私生活とかその当時の社会体制とかそんな諸事情ははずして、純粋に一つの音楽として音の連なりを分析し、理解したいと思っているのですが、
ショスタコーヴィッチに常に付きまとう「ソヴィエト」という国家の存在が、どうしてもこの作曲家の作品を複雑なものにしてしまっているようです。
反社会的な作品を書いては、政府から問題視され、そのすぐ後に「ソヴィエト、バンザイ!」な曲を書いて賞賛され、直後にまた「問題作」を提示して問題児扱いされ、さらにその直後にプロパガンダ満載の曲を作り・・・・の繰り返しで、故に作品の評価も当時と今ではばらばらで。
ソヴィエト連邦の存在、スターリン独裁政権、独ソ戦、戦後の米ソ冷戦、そしてその雪どけと、様々なものに巻き込まれた人生は、やはり作品と切り離しては考えられないのかもしれない。
難しい・・・・・結局、私にはよくわからない。
1964年、Gouldが「ソヴィエト連邦の音楽」という講演をトロント大学でやっています。
彼はデビュー間もない頃、西側からの親善大使という名目で、鉄のカーテンの向こう側、旧ソヴィエトを訪れています。
当時Bachと現代音楽が一切禁止のソヴィエトの中で、彼はBachと現代音楽だけのリサイタルを行なったんです。( ̄▽ ̄)V
そして現地を訪問中、あちらの音楽事情をとてもよく見てきたみたいです。
この講演では、彼自身のソヴィエト音楽論をとても詳しく説明してくれています。
やっぱりこの人に頼るしかない。
というわけで、Gouldの「ソヴィエト連邦の音楽」を読んでみました。
私がかろうじて理解できたことは以下の通りです。
(Gouldの表現は時々とても面白い。念のため、文章中で笑っているのは、私です。)
♪゚+.o.+゚♪゚+.o.+゚♪゚+.o.+゚♪゚+.o.+゚♪゚+.o.+゚♪♪゚+.o.+゚♪゚+.o.+゚♪゚+.o.+゚♪゚+.o.+゚♪゚+.o.+゚♪
ソヴィエト政府と芸術社会の間には不思議な関係があるようだ。
この両者は、お互いの間で調和と幻滅を、周期的パターンで展開している。
つまり、ソヴィエト経済が高成長率を上げている時はいつも、芸術社会の風変わりな振る舞いに寛容になる傾向があり、
一方、外交、経済のどちらかがうまく回っていない時には、厳しい規制、服従の要請、ナショナリズム最優先の傾向が顕著になる。
ソヴィエト政府と芸術の関係が軋んでいる本当の理由はどこにあるのだろうか。
芸術の目的と政府の目的は同じであり、芸術家も他の労働党員と同様に国家目的に尽力すべきであると、そのような観念を国民にかくもかたくなに固守させているものは何なのだろうか。
Gouldは、その原因は「共産主義」にあるのではない。・・・と見ています。
その原因は、遠くさかのぼったロシア人の歴史の中にあるのだ、と言っています。
19世紀の第二四半世紀に至るまで、ロシアには重要な作曲家による音楽がなかった。
ベートーヴェンも既に去り、ワーグナーやベルリオーズが活躍する時代になってもなお、ロシアは重要な作曲家を一人も生めずにいた。
1700年ころ、ピョートル大帝の趣味娯楽的な関心も、時代に乗り遅れまいとする欲求を超えたものではなく、
ロシア正教は、音楽を、共産主義よりもはるかに強力な権威によって規制していた。
国民の中では、あらゆる世俗音楽は禁止されていた。
ロシアでは、西洋の音楽体験に似たものは何もなかった。
和声の展開も、聖俗の技法のよくある結びつきも、人生がそうであるように、善きものも悪しきものも混合されるというルネサンスの考え方も一切が知られていなかったのだ。
根本はここにある、とGouldは推測しています。
ピョートル大帝が宮廷に西洋芸術を導入し、教会を軽視し始めた頃、芸術はほとんど輸入品だった。
ロシアの作曲家集団が伸び始めた頃、彼らが提供した音楽は、ヨーロッパの最新流行だと吹き込まれた輸入音楽の、香も褪せた模倣だった。
例えば、グリンカ・・・ベートーヴェン中期のアレグロ・アパッショナート風+ファニー・メンデルスゾーン的なサロン風+ロッシーニのイタリア風(笑)
一方、ロシア国民の魂の奥深くに独自の創造力を見出そうとする人たちもいた。
例えば、ムソルグスキー・・・技法的には未完成だったが、独特のぎこちない作風でロシア的想念の、悩み多く悲しみに満ちたありようを捉えている。
そして次の世代が登場する。
この世代は上のふたつの立場を調和させている。
つまり、西洋音楽が到達した技法の枠内で、民族的な衝撃力と、その旋律特有の陰鬱な性格のバランスをとろうと試みた。
例えば、チャイコフスキー・・・この人は、ロシア音楽巡りをする人たちが最も頻繁に訪れる人気ルートだ。(笑)
そして革命後、
基本的には何ら変化はない。
ソヴィエトの作曲家たちはいまなお、自分たちの目指す方向を見定めていないように思われる。
ヨーロッパ音楽の技法や語法に頼るべきなのか、自国文化に固有のものに集中すべきなのか。
しかし、数は少ないが、知的に洗練された作曲家もいる。
例えば、プロコフィエフ・・・Gouldが考える、革命後真に偉大なただ一人の作曲家。
そして、ショスタコーヴィッチ・・・しかし、この人は混乱した変貌を遂げてしまった。
彼の「交響曲、第一番」は澄明で創造力に溢れた自伝的作品であり、驚くべき作品だ。
来るべき世代の大作曲家になるという期待を持たせるに十分な、天才的才能を備えた青年の思春期の記録だった。
しかし、彼はそうはならなかった。
20世紀の音楽の真の悲劇、とGouldは言っています。
ショスタコーヴィッチを、体制が要求してきたすべてを骨抜きにする画一化の犠牲者と捉えるか?
いや、そうではない、とGouldは分析しています。
政府による最初の本格的妨害は、「ムツェンスク郡のマクベス夫人」の非難だった。
この非難がショスタコーヴィッチの将来のコースにどんな結果をもたらしたか、世間はちょっと劇的に考えすぎてやしないか。
(なぜなら、Gouldはこの未削除原譜を手に入れ、分析した結果、非難は正しいと思ったそうです。
これは見紛うことなく取るに足らない作品です、と言っています。)
ショスタコーヴィッチは、党によって方向を指示されるというしつこい迫害よりも、むしろロシア的な罪の意識を過剰に引き受けて苦しんだのだ。
・
・
・
・
・
・
・
長くなるのでここで打ち止めにしますが、
その後、ミャスコフスキーやストラヴィンスキーなど、様々な作曲家について、とても面白くて鋭い分析を詳しく述べています。
ご興味がある方は、是非読んでみてください。
しかし、ソヴィエト政府はとんでもない若者を招待してしまったものですね^^
Gouldがロシアを訪れたのはこの一回きりでしたが、彼はロシアをとても愛していて、最後まであちらのファンや学生との交流を続けていたそうです。
最後のゴールドベルグのビデオも、モスクワの学生たちに役立てて下さい、と送っていたそうです。
「ロシアの旅」全編がupされていました。
多分、すぐに削除されてしまうでしょうから、今のうちだけ貼っておきます。
音楽作品は純粋に「音楽」として捉えたい。
作曲家の私生活とかその当時の社会体制とかそんな諸事情ははずして、純粋に一つの音楽として音の連なりを分析し、理解したいと思っているのですが、
ショスタコーヴィッチに常に付きまとう「ソヴィエト」という国家の存在が、どうしてもこの作曲家の作品を複雑なものにしてしまっているようです。
反社会的な作品を書いては、政府から問題視され、そのすぐ後に「ソヴィエト、バンザイ!」な曲を書いて賞賛され、直後にまた「問題作」を提示して問題児扱いされ、さらにその直後にプロパガンダ満載の曲を作り・・・・の繰り返しで、故に作品の評価も当時と今ではばらばらで。
ソヴィエト連邦の存在、スターリン独裁政権、独ソ戦、戦後の米ソ冷戦、そしてその雪どけと、様々なものに巻き込まれた人生は、やはり作品と切り離しては考えられないのかもしれない。
難しい・・・・・結局、私にはよくわからない。
1964年、Gouldが「ソヴィエト連邦の音楽」という講演をトロント大学でやっています。
彼はデビュー間もない頃、西側からの親善大使という名目で、鉄のカーテンの向こう側、旧ソヴィエトを訪れています。
当時Bachと現代音楽が一切禁止のソヴィエトの中で、彼はBachと現代音楽だけのリサイタルを行なったんです。( ̄▽ ̄)V
そして現地を訪問中、あちらの音楽事情をとてもよく見てきたみたいです。
この講演では、彼自身のソヴィエト音楽論をとても詳しく説明してくれています。
やっぱりこの人に頼るしかない。
というわけで、Gouldの「ソヴィエト連邦の音楽」を読んでみました。
私がかろうじて理解できたことは以下の通りです。
(Gouldの表現は時々とても面白い。念のため、文章中で笑っているのは、私です。)
♪゚+.o.+゚♪゚+.o.+゚♪゚+.o.+゚♪゚+.o.+゚♪゚+.o.+゚♪♪゚+.o.+゚♪゚+.o.+゚♪゚+.o.+゚♪゚+.o.+゚♪゚+.o.+゚♪
ソヴィエト政府と芸術社会の間には不思議な関係があるようだ。
この両者は、お互いの間で調和と幻滅を、周期的パターンで展開している。
つまり、ソヴィエト経済が高成長率を上げている時はいつも、芸術社会の風変わりな振る舞いに寛容になる傾向があり、
一方、外交、経済のどちらかがうまく回っていない時には、厳しい規制、服従の要請、ナショナリズム最優先の傾向が顕著になる。
ソヴィエト政府と芸術の関係が軋んでいる本当の理由はどこにあるのだろうか。
芸術の目的と政府の目的は同じであり、芸術家も他の労働党員と同様に国家目的に尽力すべきであると、そのような観念を国民にかくもかたくなに固守させているものは何なのだろうか。
Gouldは、その原因は「共産主義」にあるのではない。・・・と見ています。
その原因は、遠くさかのぼったロシア人の歴史の中にあるのだ、と言っています。
19世紀の第二四半世紀に至るまで、ロシアには重要な作曲家による音楽がなかった。
ベートーヴェンも既に去り、ワーグナーやベルリオーズが活躍する時代になってもなお、ロシアは重要な作曲家を一人も生めずにいた。
1700年ころ、ピョートル大帝の趣味娯楽的な関心も、時代に乗り遅れまいとする欲求を超えたものではなく、
ロシア正教は、音楽を、共産主義よりもはるかに強力な権威によって規制していた。
国民の中では、あらゆる世俗音楽は禁止されていた。
ロシアでは、西洋の音楽体験に似たものは何もなかった。
和声の展開も、聖俗の技法のよくある結びつきも、人生がそうであるように、善きものも悪しきものも混合されるというルネサンスの考え方も一切が知られていなかったのだ。
根本はここにある、とGouldは推測しています。
ピョートル大帝が宮廷に西洋芸術を導入し、教会を軽視し始めた頃、芸術はほとんど輸入品だった。
ロシアの作曲家集団が伸び始めた頃、彼らが提供した音楽は、ヨーロッパの最新流行だと吹き込まれた輸入音楽の、香も褪せた模倣だった。
例えば、グリンカ・・・ベートーヴェン中期のアレグロ・アパッショナート風+ファニー・メンデルスゾーン的なサロン風+ロッシーニのイタリア風(笑)
一方、ロシア国民の魂の奥深くに独自の創造力を見出そうとする人たちもいた。
例えば、ムソルグスキー・・・技法的には未完成だったが、独特のぎこちない作風でロシア的想念の、悩み多く悲しみに満ちたありようを捉えている。
そして次の世代が登場する。
この世代は上のふたつの立場を調和させている。
つまり、西洋音楽が到達した技法の枠内で、民族的な衝撃力と、その旋律特有の陰鬱な性格のバランスをとろうと試みた。
例えば、チャイコフスキー・・・この人は、ロシア音楽巡りをする人たちが最も頻繁に訪れる人気ルートだ。(笑)
そして革命後、
基本的には何ら変化はない。
ソヴィエトの作曲家たちはいまなお、自分たちの目指す方向を見定めていないように思われる。
ヨーロッパ音楽の技法や語法に頼るべきなのか、自国文化に固有のものに集中すべきなのか。
しかし、数は少ないが、知的に洗練された作曲家もいる。
例えば、プロコフィエフ・・・Gouldが考える、革命後真に偉大なただ一人の作曲家。
そして、ショスタコーヴィッチ・・・しかし、この人は混乱した変貌を遂げてしまった。
彼の「交響曲、第一番」は澄明で創造力に溢れた自伝的作品であり、驚くべき作品だ。
来るべき世代の大作曲家になるという期待を持たせるに十分な、天才的才能を備えた青年の思春期の記録だった。
しかし、彼はそうはならなかった。
20世紀の音楽の真の悲劇、とGouldは言っています。
ショスタコーヴィッチを、体制が要求してきたすべてを骨抜きにする画一化の犠牲者と捉えるか?
いや、そうではない、とGouldは分析しています。
政府による最初の本格的妨害は、「ムツェンスク郡のマクベス夫人」の非難だった。
この非難がショスタコーヴィッチの将来のコースにどんな結果をもたらしたか、世間はちょっと劇的に考えすぎてやしないか。
(なぜなら、Gouldはこの未削除原譜を手に入れ、分析した結果、非難は正しいと思ったそうです。
これは見紛うことなく取るに足らない作品です、と言っています。)
ショスタコーヴィッチは、党によって方向を指示されるというしつこい迫害よりも、むしろロシア的な罪の意識を過剰に引き受けて苦しんだのだ。
・
・
・
・
・
・
・
長くなるのでここで打ち止めにしますが、
その後、ミャスコフスキーやストラヴィンスキーなど、様々な作曲家について、とても面白くて鋭い分析を詳しく述べています。
ご興味がある方は、是非読んでみてください。
しかし、ソヴィエト政府はとんでもない若者を招待してしまったものですね^^
Gouldがロシアを訪れたのはこの一回きりでしたが、彼はロシアをとても愛していて、最後まであちらのファンや学生との交流を続けていたそうです。
最後のゴールドベルグのビデオも、モスクワの学生たちに役立てて下さい、と送っていたそうです。
「ロシアの旅」全編がupされていました。
多分、すぐに削除されてしまうでしょうから、今のうちだけ貼っておきます。
Gould と GOULD [Gould]
Gouldの弾く、パルティータ5番のGigueです。
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
1957年録音とありますから、彼が25歳の頃。
まだ公の演奏活動をしていた頃の録音です。
彼はこの自分の演奏に落胆し、これが直接の原因ではないのかもしれませんが、後にコンサート活動を”ドロップ・アウト”してスタジオに篭ることになっていきます。
これ、とっても素晴らしい演奏。
何がダメなのかしら。。。と思うのですが、彼曰く、ステージ演奏の悪いクセがついてしまったのを知ってがっかりしたよと。
客席の隅々まで音を届けたい、と思うあまりに思わず音量を上げてしまったり、お客様に喜んでもらいたい、賞賛されたいと思うあまりにがんばっちゃう演奏家の心理って、ステージでは当然のことなのでしょうが、それが、音楽を歪めてしまうのだということなんですね。
一回限りのライヴ演奏で、ブラボー!の嵐と共に煙のように消えてゆく名演奏。
彼の理想は、そんなところにはなかった。
こちらは、それから6年後の1963年録音のパルティータ4番のGigueです。
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
凄いです~~~~!!
最初、ポツンと遠くの暗闇に浮き上がるテーマがだんだんと厚みを増してくる対位法のうねりに乗って、グングンとクローズアップされてくる距離感、立体感。
マイクの位置やピアノの音色、残響の加減、全てが緻密に計算されて作られた録音芸術。
これこそが、GLENN GOULD。
凄いです、本当に。
カナダ出身のいちピアニストGlenn Gouldは、ピアノにこだわり、マイクにこだわり、スタジオの中でひたすら理想の音楽を追求することで、不滅の唯一無二のピアニスト「GLENN GOULD 」を自ら作り上げていったのだと思います。
最近、カナダ国内で活躍していた若い頃やデビュー前の少年時代の録音が次々とリリースされていますが、
Gould自身はこの事態を喜んでいるでしょうか。
「GLENN GOULD」ブランドからはずれた録音たち。
もう新譜が出ることのない人だから、ファン心理としては仕方がないことなのかもしれませんが、複雑な気持ちになります。
そして、コレはおまけ。
55年デビュー盤の録音テープを解析してMIDIファイル化し、自動ピアノで再演したゼンフスタジオ盤です。
これは、どうかしら。
もしかしたら、こういう試みはGouldも面白がったかもしれませんね^^
事実、ラフマニノフ盤にはちょっと、おぉ!っと思いましたけど、でも私はいらないなぁ。
いくら忠実に再現と言われても、人の気配が感じられない、何の風も吹かない無機的な音にしか聴こえないんだなぁ。
このCDの音は、これが弾いてるのが見えちゃうんだなぁ。
感想は、一言。
「返品させろ」ですかねぇ・・・・
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
1957年録音とありますから、彼が25歳の頃。
まだ公の演奏活動をしていた頃の録音です。
彼はこの自分の演奏に落胆し、これが直接の原因ではないのかもしれませんが、後にコンサート活動を”ドロップ・アウト”してスタジオに篭ることになっていきます。
これ、とっても素晴らしい演奏。
何がダメなのかしら。。。と思うのですが、彼曰く、ステージ演奏の悪いクセがついてしまったのを知ってがっかりしたよと。
客席の隅々まで音を届けたい、と思うあまりに思わず音量を上げてしまったり、お客様に喜んでもらいたい、賞賛されたいと思うあまりにがんばっちゃう演奏家の心理って、ステージでは当然のことなのでしょうが、それが、音楽を歪めてしまうのだということなんですね。
一回限りのライヴ演奏で、ブラボー!の嵐と共に煙のように消えてゆく名演奏。
彼の理想は、そんなところにはなかった。
こちらは、それから6年後の1963年録音のパルティータ4番のGigueです。
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
凄いです~~~~!!
最初、ポツンと遠くの暗闇に浮き上がるテーマがだんだんと厚みを増してくる対位法のうねりに乗って、グングンとクローズアップされてくる距離感、立体感。
マイクの位置やピアノの音色、残響の加減、全てが緻密に計算されて作られた録音芸術。
これこそが、GLENN GOULD。
凄いです、本当に。
カナダ出身のいちピアニストGlenn Gouldは、ピアノにこだわり、マイクにこだわり、スタジオの中でひたすら理想の音楽を追求することで、不滅の唯一無二のピアニスト「GLENN GOULD 」を自ら作り上げていったのだと思います。
最近、カナダ国内で活躍していた若い頃やデビュー前の少年時代の録音が次々とリリースされていますが、
Gould自身はこの事態を喜んでいるでしょうか。
「GLENN GOULD」ブランドからはずれた録音たち。
もう新譜が出ることのない人だから、ファン心理としては仕方がないことなのかもしれませんが、複雑な気持ちになります。
そして、コレはおまけ。
55年デビュー盤の録音テープを解析してMIDIファイル化し、自動ピアノで再演したゼンフスタジオ盤です。
これは、どうかしら。
もしかしたら、こういう試みはGouldも面白がったかもしれませんね^^
事実、ラフマニノフ盤にはちょっと、おぉ!っと思いましたけど、でも私はいらないなぁ。
いくら忠実に再現と言われても、人の気配が感じられない、何の風も吹かない無機的な音にしか聴こえないんだなぁ。
このCDの音は、これが弾いてるのが見えちゃうんだなぁ。
感想は、一言。
「返品させろ」ですかねぇ・・・・
Italian concerto [Gould]
私、生意気にもチャリティー・コンサートに参加させていただき、バッハのイタリアン・コンチェルトを弾いてきました。![[どんっ(衝撃)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/161.gif)
(私だけ知らなかったのですが、この曲は「イタコン」というらしいです。同様に、ベートーヴェンは「ベトベン」というらしい。彼のソナタは「ベトソナ」というらしい。モーツァルトのソナタは「モツソナ」というらしいです。なんて不気味な・・・)
今回のこの記事の主旨は、「どうせ弾くなら他の曲を選ばせて欲しかった。」ということです。
(つまらない内容ですみません・・・)
私この曲、苦手。
2楽章は大好き。とても。
3楽章もかっこよくて好きなんです。
が、
1楽章が、ねぇ・・・なんかねぇ・・・なんというか・・・好きじゃないのです。(Bachさん、ごめんなさい!)
名曲に対して、なんとも恥知らずなのですが。
だって・・・
思い切って言ってしまうと、
この曲、ダサくないですか?
・
・
・
・
・
シーーーン・・・・
いいです、きっとこんな感想を持つのは私だけですから。
きっとこう感じてしまう私がダサイのですから、いいです、いいです。
あっ![[ひらめき]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/151.gif)
Gouldもこの曲が好きではないと言っています。
でも彼がこの曲を気に入らないのは、多分、「イタリア」→「太陽」→「南国」→「情熱」→「モワっと熱い」という図式を嫌悪する故だと思われます。
それ以上の理由は思い当たりません。
だって、彼のこの曲の演奏はとてもとても素晴らしいからです。
Gouldの、この曲の録音風景。
これがまたあまりにもインパクト大の映像なので、ある意味、私にとってのトラウマになっています。
子供の頃から長~い間見まくって、きっと見すぎたのでしょう。
だから、
①この曲を弾く時、どうしても足を組みたくなってしまう。
②1:51のように、どうしても腕をぐるっと回してしまう。(そして音をはずす。)
③自分には無理なのに、どうしてもこのテンポになってしまう。
④7:13、この部分になると、どうしても内声パートにGouldの声が「ポイパポポピ~!」と聴こえてきて動揺する。
のです。
こんな私の演奏を我慢して聴いてくださったみなさん、どうもすみませんでした。
もうちょっとマシに弾ける曲もあるのにな・・・と思いながらトボトボと家路につきました。
(私だけ知らなかったのですが、この曲は「イタコン」というらしいです。同様に、ベートーヴェンは「ベトベン」というらしい。彼のソナタは「ベトソナ」というらしい。モーツァルトのソナタは「モツソナ」というらしいです。なんて不気味な・・・)
今回のこの記事の主旨は、「どうせ弾くなら他の曲を選ばせて欲しかった。」ということです。
(つまらない内容ですみません・・・)
私この曲、苦手。
2楽章は大好き。とても。
3楽章もかっこよくて好きなんです。
が、
1楽章が、ねぇ・・・なんかねぇ・・・なんというか・・・好きじゃないのです。(Bachさん、ごめんなさい!)
名曲に対して、なんとも恥知らずなのですが。
だって・・・
思い切って言ってしまうと、
この曲、ダサくないですか?
・
・
・
・
・
シーーーン・・・・
いいです、きっとこんな感想を持つのは私だけですから。
きっとこう感じてしまう私がダサイのですから、いいです、いいです。
あっ
Gouldもこの曲が好きではないと言っています。
でも彼がこの曲を気に入らないのは、多分、「イタリア」→「太陽」→「南国」→「情熱」→「モワっと熱い」という図式を嫌悪する故だと思われます。
それ以上の理由は思い当たりません。
だって、彼のこの曲の演奏はとてもとても素晴らしいからです。
Gouldの、この曲の録音風景。
これがまたあまりにもインパクト大の映像なので、ある意味、私にとってのトラウマになっています。
子供の頃から長~い間見まくって、きっと見すぎたのでしょう。
だから、
①この曲を弾く時、どうしても足を組みたくなってしまう。
②1:51のように、どうしても腕をぐるっと回してしまう。(そして音をはずす。)
③自分には無理なのに、どうしてもこのテンポになってしまう。
④7:13、この部分になると、どうしても内声パートにGouldの声が「ポイパポポピ~!」と聴こえてきて動揺する。
のです。
こんな私の演奏を我慢して聴いてくださったみなさん、どうもすみませんでした。
もうちょっとマシに弾ける曲もあるのにな・・・と思いながらトボトボと家路につきました。
ハープシピアノ [Gould]
Gouldが弾くブランデンブルグ5番の全曲です。
1962年とありますから、約50年前の録音です。
ヴァイオリンはオスカー・シュムスキー。
フルートがジュリアス・ベーカー。(この人、うまい!)
私、この時の演奏が大好き。
スタジオ・ライブの熱気と緊張感が迫ってくる凄い演奏だと思います。
Gouldは指揮も兼ねた弾き振りをしていますが、彼のハミングがガンガン聴こえるし、途中からはもうオケそっちのけで自分の演奏に没頭して弾きまくっていて・・・とにかくすごいや。
いろんな意味で唯一無二の貴重な映像ですね。
このピアノが、Gouldが考案し命名した、かの有名な「ハープシピアノ」です。
Gould曰く、「自分がハープシコードだと思いこんでいる神経症的なピアノ」だそうです。
ハンマーのフェルトを剥がして金属を打ち込んだ改造ピアノ。
当時は相当評判が悪かったらしいです。
ステキな音色だと思うんですけど・・・
放送用音源の質が悪くてポソポソしてますが、実際はもっと美しい音色で響いたんじゃないでしょうか。
モダン・ピアノでは過分になってしまう要素を適度に抑えていて、尚且つピアノの良さを失っていない。
とても興味深い試みだと思います。
ここまでするなら本物のハープシコードを弾けばいいじゃない、という声が聞こえてきますが、それはちょっと違うんだと思います。
だって、チェンバロとピアノは違う楽器だから。
(実際彼はオルガンとチェンバロで録音を残していますが、それはまた別の視点からのアプローチで、別の話だと思います。)
Gouldは、あくまでもピアノ的な解釈でこの曲を演奏したかったのでしょう。
彼は、ピアノを惜しげもなくバンバン改造してしまう。
「20世紀になるのに、ピアノは旧態依然で古臭い。」と発言していたこともありました。
あくまでもピアノという楽器にこだわって、ピアノの可能性を追求していたのでしょうね。
(あの不細工なペダル・フリューゲルを弾かないでくれてよかった・・・・)
こう書いてくると、ジョン・ケージの「プリペアード・ピアノ」やラヴェルが使った「ピアノ・リュテアル」のことが思い出されます。
特に「ピアノ・リュテアル」には、とても興味があります。
(4:22あたりからピアノ登場)
リュートのような響き。
途中で音色を変化させることができて、ピアノの音に戻したりハープのような音に変えたりしてますね。
実物を見てみたい。
1962年とありますから、約50年前の録音です。
ヴァイオリンはオスカー・シュムスキー。
フルートがジュリアス・ベーカー。(この人、うまい!)
私、この時の演奏が大好き。
スタジオ・ライブの熱気と緊張感が迫ってくる凄い演奏だと思います。
Gouldは指揮も兼ねた弾き振りをしていますが、彼のハミングがガンガン聴こえるし、途中からはもうオケそっちのけで自分の演奏に没頭して弾きまくっていて・・・とにかくすごいや。
いろんな意味で唯一無二の貴重な映像ですね。
このピアノが、Gouldが考案し命名した、かの有名な「ハープシピアノ」です。
Gould曰く、「自分がハープシコードだと思いこんでいる神経症的なピアノ」だそうです。
ハンマーのフェルトを剥がして金属を打ち込んだ改造ピアノ。
当時は相当評判が悪かったらしいです。
ステキな音色だと思うんですけど・・・
放送用音源の質が悪くてポソポソしてますが、実際はもっと美しい音色で響いたんじゃないでしょうか。
モダン・ピアノでは過分になってしまう要素を適度に抑えていて、尚且つピアノの良さを失っていない。
とても興味深い試みだと思います。
ここまでするなら本物のハープシコードを弾けばいいじゃない、という声が聞こえてきますが、それはちょっと違うんだと思います。
だって、チェンバロとピアノは違う楽器だから。
(実際彼はオルガンとチェンバロで録音を残していますが、それはまた別の視点からのアプローチで、別の話だと思います。)
Gouldは、あくまでもピアノ的な解釈でこの曲を演奏したかったのでしょう。
彼は、ピアノを惜しげもなくバンバン改造してしまう。
「20世紀になるのに、ピアノは旧態依然で古臭い。」と発言していたこともありました。
あくまでもピアノという楽器にこだわって、ピアノの可能性を追求していたのでしょうね。
(あの不細工なペダル・フリューゲルを弾かないでくれてよかった・・・・)
こう書いてくると、ジョン・ケージの「プリペアード・ピアノ」やラヴェルが使った「ピアノ・リュテアル」のことが思い出されます。
特に「ピアノ・リュテアル」には、とても興味があります。
(4:22あたりからピアノ登場)
リュートのような響き。
途中で音色を変化させることができて、ピアノの音に戻したりハープのような音に変えたりしてますね。
実物を見てみたい。
家具になった音楽 [Gould]
書店で、「グールドのシェーンベルク 」を立ち読みしていたら、隣に立っていた女性に声をかけられた。
「あら、あなたも”グールディアン”なの?」
私は、床板の中にのめり込みそうなくらいにドッサリとぐったりしましたよ。
その不気味な名称で人をカテゴライズするのはやめていただきたい、と思いながら
「いいえ、ただのファンです。」と答えて、そそくさと帰ってきました。
”グールディアン”という言葉が大嫌い。
そういうカテゴリーに喜んで属する人が嫌い。
私が捻くれ者だからかもしれないけれど。
あなたはこういう人、と人から言われるのが嫌いだからからかもしれないけれど。
いや、それだけじゃないな・・・
ただ単に、その語感が嫌いなのかもしれない。
何の根拠もないのですが、”グールディアン”という言葉を聞くと、こんな人が![[ひらめき]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/151.gif) と頭に浮かぶ・・・・
と頭に浮かぶ・・・・
理由はないので訊かないでください。
もうじき引越しをする友人から、Gouldの本をもらいました。
「本を整理してたら出てきた。つまんないからあげる」って・・・・
そんな~。
さっきまでパラパラ見ていました。
いわゆる”グールディアン”向けの企画物ですね。
特に興味深いものはないです。
たった一つのエッセイを除いては。
高橋悠治さんの「家具になった音楽」という、Gouldが亡くなった時、高橋さんが新聞に寄せた追悼文が載っていました。
高橋悠治さんが追悼文を書いていらしたのは知っていましたが、初めてその文章を目にしました。
「家具になった音楽」
グレン・グールドが死んだ。クラッシック演奏のひとつの実験はおわった。
現代のコンサートホールで2000人以上の聴き手をもつようなピアニストは、きめこまかい表現をあきらめなければならない。指はオーケストラ全体にまけない大きい音をだす訓練をうけ、小さな音には表情というものがないのもしかたのないことだ。容量のわずかなちがいによってつくられる古典的リズム感覚は失われた。耳をすまして音を聴きとるのではなく、ステージからとどく音にひたされていればいい耳は、なまけものになった。
音の技術が進む中で1950年代にレコードがLPになり、テープ編集技術ができあがり、「電子音楽のゆめ」がうまれた。
どんな音もスタジオのなかでおもうままにつくり、くみあわせることができる、と音楽家たちはおもった。材料は自然の音にしろ、人間の声やピアノの音にしろ、聴き手がうけとるのは電圧の変化によるスピーカー膜の振動なのだから、どんな音も電子音の一種に変えられて耳にとどいている。おなじ空間のなかで、つくり手と聴き手がわかちあう音楽ではなく、聴き手のいないスタジオでうまれ、つくり手のみえないスピーカーからながれる音楽がある。音楽は密室の家具になった。テレビが映像をふくむ照明装置であるように。
グレン・グールドは、コンサートホールを捨てて、スタジオにこもった。なまの演奏の緊張と結果のむなしさに神経がたえられなかったのかもしれないが、それを時代の要求にしたてあげたのが、彼の才能だったのか。
グールドのひくバッハは、1960年代にはその演奏スタイルでひとをおどろかした。極端にはやいか、またはおそいテンポ、かんがえぬかれ、即興にみせかけた装飾音、みじかくするどい和音のくずし方。だが、それは18世紀音楽の演奏の約束ごとを踏みはずしてはいない。1970年代には古楽や古楽器の演奏にふれることもおおくなり、グールドの演奏も耳あたらしいものではなくなった。マニエリズムというレッテルをはることもできるようになった。
だが1960年代のグールドのメッセージは、演奏スタイルではなかった。コンサートホールでは聴くことができない、ということに意味があった。おなじころ、グールドの住んでいた町、カナダのトロントからマーシャル・マルクーハンが活字文化の終わりを活字で主張していた。「メディアがメッセージだ」というのが時代のあいことばだった。
この「電子時代のゆめ」は、数年間しかもちこたえることができなかった。1968年がやってきた。プラハの町にソ連の戦車が姿をあらわし、フランスとドイツで若者たちが反乱をおこし、やがてベトナムはアメリカに勝つ。中国の文化革命もあらしを過ぎ、石油危機を通りぬけると、テクノロジー信仰も、それと対立するコミューンの実験を道づれにしてくずれおちた。次の世代には身をあずけられる原理も、すすむべき道ものこされていなかった。いまメディア革命やその反対側の対抗文化にしがみついている少数は、うしろめたさを感じないではいられないはずだ。いらなくなった文明が病気となって人間にとりついている。文明に反逆する人間も、おなじ病気にかかっている。どちらも船といっしょにしずむのだ。
われわれのしらない明日がやってくる。そこにたどりつこうとしてはいけない。明日やってくる人たちのために、今日のガラクタをしまつしておくのはいい。世界というからっぽな家をひきわたして、でていけばいいのだ。
マルクーハンが死んだときは、もう忘れられていた。グールドも「メディアとしてのメッセージ」の意味がなくなったあとは、演奏スタイルの実験をくりかえすことしかできなかった。レコードというかたちがあたらしくなくなれば、聴いたことのない曲をさがしだしてくるか、だれでもがしっている曲を、聴いたことのないやり方でひくしかない。どちらにしても、そういう音楽はよけいなぜいたくで、なくてもすむものだ。
音楽なんか聴かなくても生きていける。メッセージがあるとすれば、そういうことだ。クラシック音楽が、聴き手にとってはとっくに死んだものであることに気づかずに、または気づかぬふりをして、まじめな音楽家たちは今日もしのぎをけずり、おたがいをけおとしあい、権力欲にうごかされて、はしりつづけている。音楽産業はどうしようもない不況で、大資本や国家が手をださなければなりたたないというのに、音楽市場はけっこう繁栄している。これほどのからさわぎも、そのななから、人びとにとって意味のあるあたらしい音楽文化をうみだすことに成功してはいない。
グレン・グールドは50歳で死んだ。いまの50歳といえば、まだわかい。だが、かれの死ははやすぎはしなかった。
かれだけではない。だれが死んだって、やりのこしたしごとなどないだろう。しごとの意味の方がさきに死んでしまっている。どこかでそれとしりながら、しごとを続けているのがいまの音楽家の運命だ。こういう仕事をしていれば、いのちをすりへらしても当然だ。
音楽というものがまだほろびないとすれば、明日には明日の音楽もあるだろう。だが、それを予見することはわれわれのしごとではない。いまあるような音楽が明日までも生きのびて明日をよごすことがないとおもえばこそ、音楽の明日にも希望がもてるというものだ。音楽家にとってつらい希望ではあっても。
・
・
・
・
・
Gouldは亡くなった。彼の死が早すぎたのか遅すぎたのか、私にはわからない。ただ、これからも私はずっと彼の音楽を聴き続けていくだろう。
そして、高橋悠治さんは今尚、精力的に音楽活動を続けている。
常に音楽の意義を問い続けながら。
悠治さんのBachのレコードの中にこんな文章がありました。
「楽譜は、家をたてるときの足場のようなもので、しごとがすんだら、もういらない。作曲者の意図もまた足場であり、それもすてることができる。のこるものはことばであらわすことができない。だからやるよりほかはない。
演奏にたいするこの態度は、音楽によって自己表現するロマン的なものではなく、作曲家の意図や、時には楽譜自体を解釈する古典的なものでもない。このことでおもいだすのは、中国のことわざで、「指が月をさすとき、バカは指を見る」というものだ。
演奏するとき、まずすることはきこうとし、自由な遊びをひきおこすことだ。演奏は西洋流にいえば即興のようになる。その場でその時におこらなければならないのだから。演奏者は、バッハが作曲するのとおなじ態度で演奏する。おこっていることに注意をはらい、しかも劇的効果のために音の動きをコントロールしてはならない。これは自己表現をあらかじめ排除する。それは、作曲家・演奏家・きき手がひとつのものである完全に統合された音楽的状況にたいへん近づく。演奏するのはききとることなのだ。」
「あら、あなたも”グールディアン”なの?」
私は、床板の中にのめり込みそうなくらいにドッサリとぐったりしましたよ。
その不気味な名称で人をカテゴライズするのはやめていただきたい、と思いながら
「いいえ、ただのファンです。」と答えて、そそくさと帰ってきました。
”グールディアン”という言葉が大嫌い。
そういうカテゴリーに喜んで属する人が嫌い。
私が捻くれ者だからかもしれないけれど。
あなたはこういう人、と人から言われるのが嫌いだからからかもしれないけれど。
いや、それだけじゃないな・・・
ただ単に、その語感が嫌いなのかもしれない。
何の根拠もないのですが、”グールディアン”という言葉を聞くと、こんな人が
理由はないので訊かないでください。
もうじき引越しをする友人から、Gouldの本をもらいました。
「本を整理してたら出てきた。つまんないからあげる」って・・・・
そんな~。
さっきまでパラパラ見ていました。
いわゆる”グールディアン”向けの企画物ですね。
特に興味深いものはないです。
たった一つのエッセイを除いては。
高橋悠治さんの「家具になった音楽」という、Gouldが亡くなった時、高橋さんが新聞に寄せた追悼文が載っていました。
高橋悠治さんが追悼文を書いていらしたのは知っていましたが、初めてその文章を目にしました。
「家具になった音楽」
グレン・グールドが死んだ。クラッシック演奏のひとつの実験はおわった。
現代のコンサートホールで2000人以上の聴き手をもつようなピアニストは、きめこまかい表現をあきらめなければならない。指はオーケストラ全体にまけない大きい音をだす訓練をうけ、小さな音には表情というものがないのもしかたのないことだ。容量のわずかなちがいによってつくられる古典的リズム感覚は失われた。耳をすまして音を聴きとるのではなく、ステージからとどく音にひたされていればいい耳は、なまけものになった。
音の技術が進む中で1950年代にレコードがLPになり、テープ編集技術ができあがり、「電子音楽のゆめ」がうまれた。
どんな音もスタジオのなかでおもうままにつくり、くみあわせることができる、と音楽家たちはおもった。材料は自然の音にしろ、人間の声やピアノの音にしろ、聴き手がうけとるのは電圧の変化によるスピーカー膜の振動なのだから、どんな音も電子音の一種に変えられて耳にとどいている。おなじ空間のなかで、つくり手と聴き手がわかちあう音楽ではなく、聴き手のいないスタジオでうまれ、つくり手のみえないスピーカーからながれる音楽がある。音楽は密室の家具になった。テレビが映像をふくむ照明装置であるように。
グレン・グールドは、コンサートホールを捨てて、スタジオにこもった。なまの演奏の緊張と結果のむなしさに神経がたえられなかったのかもしれないが、それを時代の要求にしたてあげたのが、彼の才能だったのか。
グールドのひくバッハは、1960年代にはその演奏スタイルでひとをおどろかした。極端にはやいか、またはおそいテンポ、かんがえぬかれ、即興にみせかけた装飾音、みじかくするどい和音のくずし方。だが、それは18世紀音楽の演奏の約束ごとを踏みはずしてはいない。1970年代には古楽や古楽器の演奏にふれることもおおくなり、グールドの演奏も耳あたらしいものではなくなった。マニエリズムというレッテルをはることもできるようになった。
だが1960年代のグールドのメッセージは、演奏スタイルではなかった。コンサートホールでは聴くことができない、ということに意味があった。おなじころ、グールドの住んでいた町、カナダのトロントからマーシャル・マルクーハンが活字文化の終わりを活字で主張していた。「メディアがメッセージだ」というのが時代のあいことばだった。
この「電子時代のゆめ」は、数年間しかもちこたえることができなかった。1968年がやってきた。プラハの町にソ連の戦車が姿をあらわし、フランスとドイツで若者たちが反乱をおこし、やがてベトナムはアメリカに勝つ。中国の文化革命もあらしを過ぎ、石油危機を通りぬけると、テクノロジー信仰も、それと対立するコミューンの実験を道づれにしてくずれおちた。次の世代には身をあずけられる原理も、すすむべき道ものこされていなかった。いまメディア革命やその反対側の対抗文化にしがみついている少数は、うしろめたさを感じないではいられないはずだ。いらなくなった文明が病気となって人間にとりついている。文明に反逆する人間も、おなじ病気にかかっている。どちらも船といっしょにしずむのだ。
われわれのしらない明日がやってくる。そこにたどりつこうとしてはいけない。明日やってくる人たちのために、今日のガラクタをしまつしておくのはいい。世界というからっぽな家をひきわたして、でていけばいいのだ。
マルクーハンが死んだときは、もう忘れられていた。グールドも「メディアとしてのメッセージ」の意味がなくなったあとは、演奏スタイルの実験をくりかえすことしかできなかった。レコードというかたちがあたらしくなくなれば、聴いたことのない曲をさがしだしてくるか、だれでもがしっている曲を、聴いたことのないやり方でひくしかない。どちらにしても、そういう音楽はよけいなぜいたくで、なくてもすむものだ。
音楽なんか聴かなくても生きていける。メッセージがあるとすれば、そういうことだ。クラシック音楽が、聴き手にとってはとっくに死んだものであることに気づかずに、または気づかぬふりをして、まじめな音楽家たちは今日もしのぎをけずり、おたがいをけおとしあい、権力欲にうごかされて、はしりつづけている。音楽産業はどうしようもない不況で、大資本や国家が手をださなければなりたたないというのに、音楽市場はけっこう繁栄している。これほどのからさわぎも、そのななから、人びとにとって意味のあるあたらしい音楽文化をうみだすことに成功してはいない。
グレン・グールドは50歳で死んだ。いまの50歳といえば、まだわかい。だが、かれの死ははやすぎはしなかった。
かれだけではない。だれが死んだって、やりのこしたしごとなどないだろう。しごとの意味の方がさきに死んでしまっている。どこかでそれとしりながら、しごとを続けているのがいまの音楽家の運命だ。こういう仕事をしていれば、いのちをすりへらしても当然だ。
音楽というものがまだほろびないとすれば、明日には明日の音楽もあるだろう。だが、それを予見することはわれわれのしごとではない。いまあるような音楽が明日までも生きのびて明日をよごすことがないとおもえばこそ、音楽の明日にも希望がもてるというものだ。音楽家にとってつらい希望ではあっても。
・
・
・
・
・
Gouldは亡くなった。彼の死が早すぎたのか遅すぎたのか、私にはわからない。ただ、これからも私はずっと彼の音楽を聴き続けていくだろう。
そして、高橋悠治さんは今尚、精力的に音楽活動を続けている。
常に音楽の意義を問い続けながら。
悠治さんのBachのレコードの中にこんな文章がありました。
「楽譜は、家をたてるときの足場のようなもので、しごとがすんだら、もういらない。作曲者の意図もまた足場であり、それもすてることができる。のこるものはことばであらわすことができない。だからやるよりほかはない。
演奏にたいするこの態度は、音楽によって自己表現するロマン的なものではなく、作曲家の意図や、時には楽譜自体を解釈する古典的なものでもない。このことでおもいだすのは、中国のことわざで、「指が月をさすとき、バカは指を見る」というものだ。
演奏するとき、まずすることはきこうとし、自由な遊びをひきおこすことだ。演奏は西洋流にいえば即興のようになる。その場でその時におこらなければならないのだから。演奏者は、バッハが作曲するのとおなじ態度で演奏する。おこっていることに注意をはらい、しかも劇的効果のために音の動きをコントロールしてはならない。これは自己表現をあらかじめ排除する。それは、作曲家・演奏家・きき手がひとつのものである完全に統合された音楽的状況にたいへん近づく。演奏するのはききとることなのだ。」
タグ:高橋悠治
グレン・グールドをめぐる32章をめぐって [Gould]
今年もあと残すところ数日になりましたね。
今年最後の記事は、やっぱりGouldのことで締めくくらなくては。
Gouldを題材にしたドキュメンタリーは多々ありますが、彼を基に作られた映画は今のところひとつだけ。
”Thirty Two Short Films about Glenn Gould” (グレン・グールドをめぐる32章)
Gouldの死後、約10年後の1993年に作られた映画で、タイトルの32章は勿論、ゴールドベルク変奏曲の32曲からきています。
彼の発言や人生の逸話を32のショートムービーに断片的に繋いだ、ユニークな映画です。
面白いかと聞かれると・・・・う~ん・・・ビミョウですね~^^;
全編、暗くて深刻で。
そういう一面も当然あったんでしょうが、もっと無邪気で楽しい面もあったはず。
描かれているエピソードは事実には間違いないのでしょうが、事実のどの部分に焦点を当て、どのように描くかは製作者の主観によるものだから、まぁ、こんな捉え方もあるのかなとも思いますが、悲壮感に満ちた暗い人生とは反対の、とても充実した、自分の理想を貫いた人生を歩んだ人だと、個人的には思っているのですよ。
最初の「Gould meets Gould」は、実際に彼が雑誌に書いたセルフ・インタビューの一節です。
GouldがGouldにインタビューをするのですが、これがとても面白いです。
こんなに深刻ではなく、もっとウィットに溢れていて楽しい文章ながら鋭く真髄を突いた内容で素晴らしい。
例によって、また日本語訳が違いますね。
Gould : グールドさん、話したくないことは?
Gould : 別にないですよ、音楽のこと以外は。
と、ややウケするとこなのに・・・・
(あと、この役者さんに言いたい。40代のGouldは、こんなじいさんじゃないですから。)
当時のインタビューを読んでみると、彼がステージを引退した「ドロップ・アウト」に関するものがとても多くて驚きます。
ステージに上がらないことがそんなに特別なことだったのかと。
当時は今のように多彩なメディアがなかったから、演奏家の表現手段はもっぱらステージの上だったのでしょうね。
だから、彼が自分のスタンスをどれだけ説明しても、当時の人にはなかなか理解されなかったのでしょう。
Gouldは、その他大勢の群集と化したコンサートホールの聴衆ではなく、アパートの部屋で、お茶の間で、リビング・ルームでレコードプレイヤーを操作して熱心に耳を傾ける、私たち個人、一人ひとりに音楽を届けたかったんだと思う。
そして、サーカス紛いの超絶技巧を披露して拍手喝采を浴びる、何かのショーのようなステージ・パフォーマンスを嫌っていました。
純粋に音楽を伝えるためには、演奏者は無名であるべきだと。
演奏家のいでたちなど、どうでもいいじゃないか。
どんな低い椅子に座っていようが、
弾きながら歌おうが、指揮をしようが、
真夏にオーバーコートを着ようが、
そんなこと、どうでもいいじゃないか。
イケメンだろうが禿げてようがそんなの音楽と関係ないだろ、ほっといて下さいな、と思っていたのでしょうね。
ヒドイね、これ。これ見て笑う人がいるんだね。

人嫌いのGould・・・・自分の真剣で一生懸命の行動が曲解され利用されれば、人間不信にもなってしまうよ。
そう言えば、、ビートルズもライブでのショー・パフォーマンスに疑問を感じてステージを降りたのですよね。
その時も大騒ぎになったのでしょうか。
どちらも、レコーディングをアートと考える方向性を持っていたのも興味深いです。
コンセプト・アルバムという発想はこの頃から出てきたものでしょう。
ここの場面はちょっと怖い。
ふ~ん・・・・
ちなみにバッハの亡くなった年齢は・・・・65歳・・・・・あっ![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif) ・・・・・
・・・・・
この映画の監督はフランソワ・ジラールさんです。
彼の「レッド・ヴァイオリン」はとても素敵な映画です。
最近では、シルク・ド・ソレイユの演出を手がけて来日もしていました。
最後に、この映画で私が一番好きな場面です。
とてもGouldらしくて印象的。
素晴らしい彼に、乾杯!![[喫茶店]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/51.gif)
みなさん、良いお年を!
今年最後の記事は、やっぱりGouldのことで締めくくらなくては。
Gouldを題材にしたドキュメンタリーは多々ありますが、彼を基に作られた映画は今のところひとつだけ。
”Thirty Two Short Films about Glenn Gould” (グレン・グールドをめぐる32章)
Gouldの死後、約10年後の1993年に作られた映画で、タイトルの32章は勿論、ゴールドベルク変奏曲の32曲からきています。
彼の発言や人生の逸話を32のショートムービーに断片的に繋いだ、ユニークな映画です。
面白いかと聞かれると・・・・う~ん・・・ビミョウですね~^^;
全編、暗くて深刻で。
そういう一面も当然あったんでしょうが、もっと無邪気で楽しい面もあったはず。
描かれているエピソードは事実には間違いないのでしょうが、事実のどの部分に焦点を当て、どのように描くかは製作者の主観によるものだから、まぁ、こんな捉え方もあるのかなとも思いますが、悲壮感に満ちた暗い人生とは反対の、とても充実した、自分の理想を貫いた人生を歩んだ人だと、個人的には思っているのですよ。
最初の「Gould meets Gould」は、実際に彼が雑誌に書いたセルフ・インタビューの一節です。
GouldがGouldにインタビューをするのですが、これがとても面白いです。
こんなに深刻ではなく、もっとウィットに溢れていて楽しい文章ながら鋭く真髄を突いた内容で素晴らしい。
例によって、また日本語訳が違いますね。
Gould : グールドさん、話したくないことは?
Gould : 別にないですよ、音楽のこと以外は。
と、ややウケするとこなのに・・・・
(あと、この役者さんに言いたい。40代のGouldは、こんなじいさんじゃないですから。)
当時のインタビューを読んでみると、彼がステージを引退した「ドロップ・アウト」に関するものがとても多くて驚きます。
ステージに上がらないことがそんなに特別なことだったのかと。
当時は今のように多彩なメディアがなかったから、演奏家の表現手段はもっぱらステージの上だったのでしょうね。
だから、彼が自分のスタンスをどれだけ説明しても、当時の人にはなかなか理解されなかったのでしょう。
Gouldは、その他大勢の群集と化したコンサートホールの聴衆ではなく、アパートの部屋で、お茶の間で、リビング・ルームでレコードプレイヤーを操作して熱心に耳を傾ける、私たち個人、一人ひとりに音楽を届けたかったんだと思う。
そして、サーカス紛いの超絶技巧を披露して拍手喝采を浴びる、何かのショーのようなステージ・パフォーマンスを嫌っていました。
純粋に音楽を伝えるためには、演奏者は無名であるべきだと。
演奏家のいでたちなど、どうでもいいじゃないか。
どんな低い椅子に座っていようが、
弾きながら歌おうが、指揮をしようが、
真夏にオーバーコートを着ようが、
そんなこと、どうでもいいじゃないか。
イケメンだろうが禿げてようがそんなの音楽と関係ないだろ、ほっといて下さいな、と思っていたのでしょうね。
ヒドイね、これ。これ見て笑う人がいるんだね。

人嫌いのGould・・・・自分の真剣で一生懸命の行動が曲解され利用されれば、人間不信にもなってしまうよ。
そう言えば、、ビートルズもライブでのショー・パフォーマンスに疑問を感じてステージを降りたのですよね。
その時も大騒ぎになったのでしょうか。
どちらも、レコーディングをアートと考える方向性を持っていたのも興味深いです。
コンセプト・アルバムという発想はこの頃から出てきたものでしょう。
ここの場面はちょっと怖い。
ふ~ん・・・・
ちなみにバッハの亡くなった年齢は・・・・65歳・・・・・あっ
この映画の監督はフランソワ・ジラールさんです。
彼の「レッド・ヴァイオリン」はとても素敵な映画です。
最近では、シルク・ド・ソレイユの演出を手がけて来日もしていました。
最後に、この映画で私が一番好きな場面です。
とてもGouldらしくて印象的。
素晴らしい彼に、乾杯!
みなさん、良いお年を!
Schoenberg, Webern and Berg [Gould]
「新ウィーン楽派」の3人の作曲家、シェーンベルク、ウェーベルン、ベルクはひとつに結び付けられて語られることが多いですね。
個人的には、シェーンベルクは「月に憑かれたピエロ」あたりになるともうお手上げです。
ウェーベルンについては、バッハの「音楽の捧げ物」のアレンジ(例の音色フーガの技法を駆使したもの)には感動しますが、それ以外ではあまり興味が持てません。
この3人のなかでは、ベルクが、実は大好きなんです。かなり退廃的で不健康な音楽かもしれませんが、とても美しい・・・・
Gouldが、この3人の作曲家のことを、実に的確に(と、個人的には思う)語っているビデオがあります。
ブルーノ・モンサンジョン制作の「The Alchemist 」。
とてもオリジナルな解釈ですが、とてもとても面白い視点でこの3人を解説してくれています。
私、このビデオが大好きなんです。
モンサンジョンさんは、本当の意味でGouldの良き理解者だったんですね。
ただ残念なことに、なんとも日本語字幕がお粗末で、ひどいのよ~。
意味わかんないところ多々。音楽用語めちゃくちゃ。
クレームしちゃおうかしら・・・
なので、精一杯わかる範囲で訳してみました。
(この人の頭の回転についていけない!早口だし、話がボンボコ飛んで・・・)
世間一般に認められている意見では、ウェーベルンはある意味、シェーンベルクのメッセージやテクニックを未来につなげているということになっています。
これらはその後、ブーレーズやセリー主義の信奉者たちによって発展させられていきます。
一方ベルクは、比較的保守的な書法を用いているので、彼の過去を、彼が出てきたその世界を体現しているということになっています。
そして、シェーンベルクは、その中間的なものを体現しているということになっています。
でも、私(Gould)は、この3人の関係をもっと違うように見ています。
シェーンベルクは、一種の狂熱的な人物。
相手が聴衆だろうと、あたりかまわず怒りの言葉をはきちらす、旧約聖書の巨人のような人物。
(自分自身や自分の役割や自分の作品に対する激しい思い入れという点で)ほとんどベートーヴェン的とも言える人物のように思えます。
(ここで、シェーンベルクの組曲Op.25のインテルメッツォを怒った顔で弾いています)
ウェーベルンは、その初期作品が証拠なんですが、調性音楽を書いているときはあまり幸せではなかった。
初期の調性音楽はあまり出来が良くない。
しかし彼は、その生涯のずっと後になって、とても美しい細密画のようなテクニックを作り上げ、音楽におけるサミュエル・ベケットやピエト・モンドリアンのような存在になった。
(ここで、ウェーベルンの変奏曲Op.27)
ベルクは、より良く構成された、より優れたテクニックを駆使するムソルグスキーのように見えます。
コーヒーハウスに入り浸っている、かなりノイローゼがかった耽美風の人物。
自分が示そうとする自分自身についての自伝的イメージに囚われた人物。
そして、ものすごく情熱的な音楽を書くんです。
だけど、こういう情熱には似つかわしくないテクニックの力を借りてね。
(ここで、ベルクのソナタOp.1)
ベルクの生涯には、実は音楽家としてスタートしたばかりの頃ですが、まさに彼にピッタリの音楽言語で、まるで水を得た魚のように作品を書いている時期があります。
それは、やがて無調性になるものに近い音楽言語、あるいは少なくとも調性の終末を予告するような音楽言語で、そこではワーグナー風のライト・モチーフを使っているのですが、それらを古いソナタ・アレグロのフォームの中に入れているのです。
それ以後、年を重ねながらベルクが負っていった問題は、彼が古い形式と新しいテクニックを使い続けたところにあります。
これらの形式とテクニックはうまく結びつかなかったんだ。
モンサンジョン:ベルクは彼の音楽言語の成熟には辿りつけなかったと?
Gould :いや、そんなことはないよ。彼は明らかに彼自身の音楽言語を見出しましたよ。彼の「ヴァイオリン・コンチェルト」や「叙情組曲」を聴くと、あっベルク!ってすぐにわかりますから。
おそらく彼は、素人がすぐに誰だか聴きわけられる唯一の十二音技法の作曲家でしょう。
ただ彼は、最初から最後まで、まったくの折衷主義者だった。
私は、ベルクのことを思うとたまらない感じになるんだ、彼は彼自身の名声のためには丁度良いときにこの世を去った・・・・あ~っ別に彼の早死にを期待していたわけではないんですよ!ただ、彼がもっと長生きしていたら、彼に備わった感傷的な性質、時と共にますます支配的になってゆくこの性質は、(彼の後期の作品、特に「ヴァイオリン・コンチェルト」などのね)、もし彼がもっと生きていたら、彼が若い頃に作り上げた素晴らしく構成された有機的構造を犠牲にしてどんどん増大していったことでしょう。
私は、とても奇妙な倒錯した理論をもっているんです。もちろん間違っているのかも知れませんが、なんと言えばいいのか・・・・様々なスタイルの混合がテクノロジーの介入によって音楽の将来を表すというものです。
様々なスタイルはOp.1よりも説得力を持ってミックスされることは決してないという理論です。その理論のもとでは、多くの場合、作曲家は彼の初期作品より優れたものを書くことは決してないのです。
フランスのビゼーが初期作品より優れたものを何一つ書いていないなどとは言いませんよ。
彼が「交響曲ハ長調」を書いたのは17歳の時です。わぉ!
ベルクがソナタOp.1よりも優れたものを書いていないとも思っていません。
ただ、シェーンベルクはその作品を気に入っていなかった。それで何故だろうと考えたんです。
ベルクはソナタ・アレグロの様々な要求に従いながら、ワーグナーのライト・モチーフに似たとても短い3つのモチーフを使っています。(パンパパ~~~ンと歌ってみせる)
これらのモチーフを基に、全体を提示部、展開部、再現部という枠組みに置きながら非常に緻密な構造を築き上げたのです。
当然、このことは彼にとって厄介なことになりました。彼は古い形式から抜け出して、完璧に結合してしまっているこれらの素材を新しい形式にあてはめる方法を見つけることができなかったんだ。
方や、ウェーベルンはこういうことをうまくやってのけたわけで。
ウェーベルンが未来を表し、ベルクが過去を表すと言われているのはそのためですね。
でもこれでは単純視しすぎると思いますよ。
現実にはベルクは1908年、22~23歳の時にOp.1を書き、それが当たったんですから。
モンサンジョン:ベルクはあなたがこのように語ることを認めてくれたでしょうか?
Gould :たぶん、だめでしょうね!(笑) でも私はこの理論が気に入ってるんだもん!(笑)
個人的には、シェーンベルクは「月に憑かれたピエロ」あたりになるともうお手上げです。
ウェーベルンについては、バッハの「音楽の捧げ物」のアレンジ(例の音色フーガの技法を駆使したもの)には感動しますが、それ以外ではあまり興味が持てません。
この3人のなかでは、ベルクが、実は大好きなんです。かなり退廃的で不健康な音楽かもしれませんが、とても美しい・・・・
Gouldが、この3人の作曲家のことを、実に的確に(と、個人的には思う)語っているビデオがあります。
ブルーノ・モンサンジョン制作の「The Alchemist 」。
とてもオリジナルな解釈ですが、とてもとても面白い視点でこの3人を解説してくれています。
私、このビデオが大好きなんです。
モンサンジョンさんは、本当の意味でGouldの良き理解者だったんですね。
ただ残念なことに、なんとも日本語字幕がお粗末で、ひどいのよ~。
意味わかんないところ多々。音楽用語めちゃくちゃ。
クレームしちゃおうかしら・・・
なので、精一杯わかる範囲で訳してみました。
(この人の頭の回転についていけない!早口だし、話がボンボコ飛んで・・・)
世間一般に認められている意見では、ウェーベルンはある意味、シェーンベルクのメッセージやテクニックを未来につなげているということになっています。
これらはその後、ブーレーズやセリー主義の信奉者たちによって発展させられていきます。
一方ベルクは、比較的保守的な書法を用いているので、彼の過去を、彼が出てきたその世界を体現しているということになっています。
そして、シェーンベルクは、その中間的なものを体現しているということになっています。
でも、私(Gould)は、この3人の関係をもっと違うように見ています。
シェーンベルクは、一種の狂熱的な人物。
相手が聴衆だろうと、あたりかまわず怒りの言葉をはきちらす、旧約聖書の巨人のような人物。
(自分自身や自分の役割や自分の作品に対する激しい思い入れという点で)ほとんどベートーヴェン的とも言える人物のように思えます。
(ここで、シェーンベルクの組曲Op.25のインテルメッツォを怒った顔で弾いています)
ウェーベルンは、その初期作品が証拠なんですが、調性音楽を書いているときはあまり幸せではなかった。
初期の調性音楽はあまり出来が良くない。
しかし彼は、その生涯のずっと後になって、とても美しい細密画のようなテクニックを作り上げ、音楽におけるサミュエル・ベケットやピエト・モンドリアンのような存在になった。
(ここで、ウェーベルンの変奏曲Op.27)
ベルクは、より良く構成された、より優れたテクニックを駆使するムソルグスキーのように見えます。
コーヒーハウスに入り浸っている、かなりノイローゼがかった耽美風の人物。
自分が示そうとする自分自身についての自伝的イメージに囚われた人物。
そして、ものすごく情熱的な音楽を書くんです。
だけど、こういう情熱には似つかわしくないテクニックの力を借りてね。
(ここで、ベルクのソナタOp.1)
ベルクの生涯には、実は音楽家としてスタートしたばかりの頃ですが、まさに彼にピッタリの音楽言語で、まるで水を得た魚のように作品を書いている時期があります。
それは、やがて無調性になるものに近い音楽言語、あるいは少なくとも調性の終末を予告するような音楽言語で、そこではワーグナー風のライト・モチーフを使っているのですが、それらを古いソナタ・アレグロのフォームの中に入れているのです。
それ以後、年を重ねながらベルクが負っていった問題は、彼が古い形式と新しいテクニックを使い続けたところにあります。
これらの形式とテクニックはうまく結びつかなかったんだ。
モンサンジョン:ベルクは彼の音楽言語の成熟には辿りつけなかったと?
Gould :いや、そんなことはないよ。彼は明らかに彼自身の音楽言語を見出しましたよ。彼の「ヴァイオリン・コンチェルト」や「叙情組曲」を聴くと、あっベルク!ってすぐにわかりますから。
おそらく彼は、素人がすぐに誰だか聴きわけられる唯一の十二音技法の作曲家でしょう。
ただ彼は、最初から最後まで、まったくの折衷主義者だった。
私は、ベルクのことを思うとたまらない感じになるんだ、彼は彼自身の名声のためには丁度良いときにこの世を去った・・・・あ~っ別に彼の早死にを期待していたわけではないんですよ!ただ、彼がもっと長生きしていたら、彼に備わった感傷的な性質、時と共にますます支配的になってゆくこの性質は、(彼の後期の作品、特に「ヴァイオリン・コンチェルト」などのね)、もし彼がもっと生きていたら、彼が若い頃に作り上げた素晴らしく構成された有機的構造を犠牲にしてどんどん増大していったことでしょう。
私は、とても奇妙な倒錯した理論をもっているんです。もちろん間違っているのかも知れませんが、なんと言えばいいのか・・・・様々なスタイルの混合がテクノロジーの介入によって音楽の将来を表すというものです。
様々なスタイルはOp.1よりも説得力を持ってミックスされることは決してないという理論です。その理論のもとでは、多くの場合、作曲家は彼の初期作品より優れたものを書くことは決してないのです。
フランスのビゼーが初期作品より優れたものを何一つ書いていないなどとは言いませんよ。
彼が「交響曲ハ長調」を書いたのは17歳の時です。わぉ!
ベルクがソナタOp.1よりも優れたものを書いていないとも思っていません。
ただ、シェーンベルクはその作品を気に入っていなかった。それで何故だろうと考えたんです。
ベルクはソナタ・アレグロの様々な要求に従いながら、ワーグナーのライト・モチーフに似たとても短い3つのモチーフを使っています。(パンパパ~~~ンと歌ってみせる)
これらのモチーフを基に、全体を提示部、展開部、再現部という枠組みに置きながら非常に緻密な構造を築き上げたのです。
当然、このことは彼にとって厄介なことになりました。彼は古い形式から抜け出して、完璧に結合してしまっているこれらの素材を新しい形式にあてはめる方法を見つけることができなかったんだ。
方や、ウェーベルンはこういうことをうまくやってのけたわけで。
ウェーベルンが未来を表し、ベルクが過去を表すと言われているのはそのためですね。
でもこれでは単純視しすぎると思いますよ。
現実にはベルクは1908年、22~23歳の時にOp.1を書き、それが当たったんですから。
モンサンジョン:ベルクはあなたがこのように語ることを認めてくれたでしょうか?
Gould :たぶん、だめでしょうね!(笑) でも私はこの理論が気に入ってるんだもん!(笑)
楽譜の向こう側 [Gould]
「紙に書かれた黒い記号・・・・我々は白い紙に黒い記号を書く。どこにでもある単なる事実だ。しかし音楽は単なる事実以上に、はるかに微妙なコミュニケーションなのだ。作曲家は、自分の内に偉大な旋律が湧き上がったとき、せいぜい紙にそれを書き記すことしかできない。それを音楽とよんでいるわけだが、本当は違う。それは紙にしかすぎない。人によっては、紙の上に記された記号を単に機械的に再現すべきだと信じているものもいるが、私はそうは思わない。それを超えたところまで行くべきなのだ。機械的な考えが強くなる一方の現在、我々はそうした概念から作曲家を守らなければならない。」
これは、Gouldに語ったストコフスキーの言葉です。
楽譜を読み解くだけではない。
楽譜を超えたところ、楽譜の向こう側に思いを馳せる人。
Gouldもストコフスキーも、そういう人なんだと思う。
楽譜の向こう側、もしかしたら、作曲家自身も知らないもうひとつの世界。
「ダークサイド・オブ・ザ・ムーン」が見える人。
Gouldもストコフスキーも、そういう人なんだ。
ピアノは猫でも弾けるらしい。
確かに。
猫が弾いても、私が弾いても「ド」は「ド」。(もっとも、厳密に言えば猫にピアノは弾けないよ、だってペダルに足が届かないじゃない)
ペダルに足は届くけど、私は猫以上に演奏技術があるわけではない。
技術って、共産国のオリンピック選手並みに鍛えれば、ある程度手に入りそうじゃない?
スポーツ選手のようにトレーニングを積めば、速く正確に鍵盤を叩くことはできるかもしれない。
でも、それって音楽することとは別の次元の世界のような気がします。
だから難曲を楽々と弾きこなすだけの、超絶技巧を誇るピアニストにはあまり興味がない。(もっとも、Gouldは超絶技巧持ってますけど)
自分のキャパシティーはたかが知れてるし、せいぜい自分が手に出来るだろう僅かな技術の取得に費やす時間と労力がもったいない気がします。
限られた自分の能力と時間の中で、どうしても持ちたいのは、楽譜の「向こう側」の世界。
厳密に言えば、楽譜の向こう側の存在を在らしめる、豊かで自由な想像力と霊感を生み出す「脳細胞」。
鉛を黄金に変える賢者の石。
天才バッハの賢者の石も、紙に載せてしまうとやはり黒い記号の塊だ。

このたった24小節のシンプルな記号を、3分間の素晴らしい生命体に変えてしまう錬金術。
どこに行けば売ってますかねぇ・・・・
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
Glenn Gould " Sarabande "
これは、Gouldに語ったストコフスキーの言葉です。
楽譜を読み解くだけではない。
楽譜を超えたところ、楽譜の向こう側に思いを馳せる人。
Gouldもストコフスキーも、そういう人なんだと思う。
楽譜の向こう側、もしかしたら、作曲家自身も知らないもうひとつの世界。
「ダークサイド・オブ・ザ・ムーン」が見える人。
Gouldもストコフスキーも、そういう人なんだ。
ピアノは猫でも弾けるらしい。
確かに。
猫が弾いても、私が弾いても「ド」は「ド」。(もっとも、厳密に言えば猫にピアノは弾けないよ、だってペダルに足が届かないじゃない)
ペダルに足は届くけど、私は猫以上に演奏技術があるわけではない。
技術って、共産国のオリンピック選手並みに鍛えれば、ある程度手に入りそうじゃない?
スポーツ選手のようにトレーニングを積めば、速く正確に鍵盤を叩くことはできるかもしれない。
でも、それって音楽することとは別の次元の世界のような気がします。
だから難曲を楽々と弾きこなすだけの、超絶技巧を誇るピアニストにはあまり興味がない。(もっとも、Gouldは超絶技巧持ってますけど)
自分のキャパシティーはたかが知れてるし、せいぜい自分が手に出来るだろう僅かな技術の取得に費やす時間と労力がもったいない気がします。
限られた自分の能力と時間の中で、どうしても持ちたいのは、楽譜の「向こう側」の世界。
厳密に言えば、楽譜の向こう側の存在を在らしめる、豊かで自由な想像力と霊感を生み出す「脳細胞」。
鉛を黄金に変える賢者の石。
天才バッハの賢者の石も、紙に載せてしまうとやはり黒い記号の塊だ。

このたった24小節のシンプルな記号を、3分間の素晴らしい生命体に変えてしまう錬金術。
どこに行けば売ってますかねぇ・・・・
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
Glenn Gould " Sarabande "
反ピアニスト [Gould]
今日のMineosaurusさんの記事を拝見していて、いつもながら記事に感動し、流れていたブルックナーに感動し、いろいろなことを考えました。
ブルックナーの弦楽五重奏曲、アダージオ。
大好きな曲です。
これを聴きながらGouldのインタビューを思い出していました。
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
インタビュアー(ヴィンセント・トヴェル):何の曲ですか?
GG:ブルックナーの弦楽五重奏曲です。
VT:こんなロマンティックな曲が聴けるとは思っていませんでした。
GG:彼の最高傑作だと思います。ブルックナーの曲で、クライマックスの度に金管が轟かないのはこの曲だけです。素晴らしい。
VT:弦楽器の音楽ですね。個人的な楽しみのためにしか弾けませんね。
GG:そうですね。同時代のほとんどのピアノ曲よりブルックナーをピアノで弾く方がずっと楽しいんです。
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
ドイツのことを語りだすと、何故かこの人はドイツ訛りになる・・・・(笑)
Gouldの弾くバッハに魅了されてずっと聴き続けていますが、実は私が一番好きなGouldは、ここにいます。
僕はピアニストではないと言い、30歳になったら作曲家になりたいと言い、50歳になったら指揮者になりたいと言っていたGould。
反ピアノ的な姿勢で演奏するピアニスト。
ピアニストでありながらピアニスティックなものを嫌い、ピアノを弾きながらピアノの向こうにもっともっと大きな音の宇宙を見ていたGould。
「僕が日頃から抱いている確信は、重要な作曲家の大半にとってピアノは管弦楽の代替物であったということです。ピアノは本当は弦楽四重奏や合奏協奏曲の編成や大管弦楽などの形で演奏されるべき音楽を響かせるために存在してきたのです。脳裏に別の音響体系を持たずにピアノ曲を書いた作曲家に一流の人はほとんどいないと思います。」
自分のことで恐縮なのですが、子供の頃相次いでピアノの先生に嫌われてしまった私が、最終的にレッスンを見ていただいたのは作曲家の先生でした。
自分にとってはこれがとても良かったと思っています。
勿論、技術的なこと、演奏の奥義などは教えていただかなかったので、未だにピアノの腕は・・・・・・ですが、それには代えられない沢山のことを教えていただきました。
当時の楽譜を見てみると、ここは金管、ここはチェロ、などと書き込みがしてあります。
作曲家の方はピアノの曲も管弦楽を分析する目で解釈するんだなぁ、と思ったものです。
Gouldは、管弦楽やオペラなどもピアノで自由自在に再現できたそうです。
記録として残っているのは彼が自分でアレンジ、録音したワーグナーの作品が少しとラヴェルの「ラ・ヴァルス」くらいで、後はこの音源のように自分の楽しみのために限られてしまっているのが残念です。
両手で足らないパートは自分で歌って、今日はどのパートを弾いてどこを歌おうかなんていいながら楽しんでいたそうで。
なんて素晴らしい。
もっと沢山、管弦楽物の録音を残して欲しかったなと思います。
自分も密かにアレンジなどというものを試みているのですが、全然だめなのね~・・・・
オーケストラやアンサンブルの曲をピアノに移すとき、対位法をうまく操れないとぺっちゃんこになってしまう。
Gouldが言うところの「素晴らしく陳腐なるもの」、「教会の親睦会でのいわゆる”ブンチャッチャ”風の音楽」。
なんて的確で素晴らしい表現(汗)
・・・・・・・
さて、秋の夜長、少しでも勉強しよ。
ブルックナーの弦楽五重奏曲、アダージオ。
大好きな曲です。
これを聴きながらGouldのインタビューを思い出していました。
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
インタビュアー(ヴィンセント・トヴェル):何の曲ですか?
GG:ブルックナーの弦楽五重奏曲です。
VT:こんなロマンティックな曲が聴けるとは思っていませんでした。
GG:彼の最高傑作だと思います。ブルックナーの曲で、クライマックスの度に金管が轟かないのはこの曲だけです。素晴らしい。
VT:弦楽器の音楽ですね。個人的な楽しみのためにしか弾けませんね。
GG:そうですね。同時代のほとんどのピアノ曲よりブルックナーをピアノで弾く方がずっと楽しいんです。
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
ドイツのことを語りだすと、何故かこの人はドイツ訛りになる・・・・(笑)
Gouldの弾くバッハに魅了されてずっと聴き続けていますが、実は私が一番好きなGouldは、ここにいます。
僕はピアニストではないと言い、30歳になったら作曲家になりたいと言い、50歳になったら指揮者になりたいと言っていたGould。
反ピアノ的な姿勢で演奏するピアニスト。
ピアニストでありながらピアニスティックなものを嫌い、ピアノを弾きながらピアノの向こうにもっともっと大きな音の宇宙を見ていたGould。
「僕が日頃から抱いている確信は、重要な作曲家の大半にとってピアノは管弦楽の代替物であったということです。ピアノは本当は弦楽四重奏や合奏協奏曲の編成や大管弦楽などの形で演奏されるべき音楽を響かせるために存在してきたのです。脳裏に別の音響体系を持たずにピアノ曲を書いた作曲家に一流の人はほとんどいないと思います。」
自分のことで恐縮なのですが、子供の頃相次いでピアノの先生に嫌われてしまった私が、最終的にレッスンを見ていただいたのは作曲家の先生でした。
自分にとってはこれがとても良かったと思っています。
勿論、技術的なこと、演奏の奥義などは教えていただかなかったので、未だにピアノの腕は・・・・・・ですが、それには代えられない沢山のことを教えていただきました。
当時の楽譜を見てみると、ここは金管、ここはチェロ、などと書き込みがしてあります。
作曲家の方はピアノの曲も管弦楽を分析する目で解釈するんだなぁ、と思ったものです。
Gouldは、管弦楽やオペラなどもピアノで自由自在に再現できたそうです。
記録として残っているのは彼が自分でアレンジ、録音したワーグナーの作品が少しとラヴェルの「ラ・ヴァルス」くらいで、後はこの音源のように自分の楽しみのために限られてしまっているのが残念です。
両手で足らないパートは自分で歌って、今日はどのパートを弾いてどこを歌おうかなんていいながら楽しんでいたそうで。
なんて素晴らしい。
もっと沢山、管弦楽物の録音を残して欲しかったなと思います。
自分も密かにアレンジなどというものを試みているのですが、全然だめなのね~・・・・
オーケストラやアンサンブルの曲をピアノに移すとき、対位法をうまく操れないとぺっちゃんこになってしまう。
Gouldが言うところの「素晴らしく陳腐なるもの」、「教会の親睦会でのいわゆる”ブンチャッチャ”風の音楽」。
なんて的確で素晴らしい表現(汗)
・・・・・・・
さて、秋の夜長、少しでも勉強しよ。